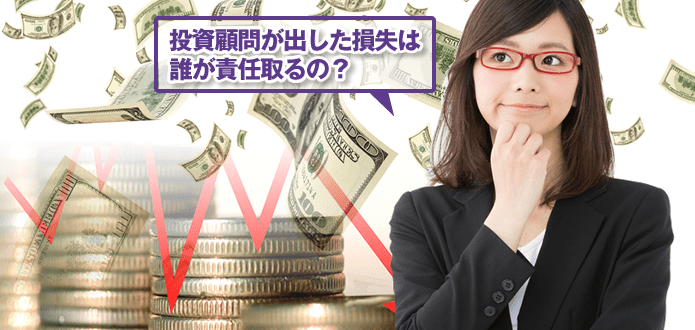「助言ミスはだれの責任?」
投資顧問の助言で生じた損失って誰が責任を負うと思いますか?
この質問には明確な答えがありますが、利用者の立場としては「助言に従ったんだから、責任は投資顧問側に取ってほしい」と思うはずです。それに投資の失敗の責任を取ってくれない投資顧問があればその会社の事を「悪徳な会社」と感じるかもしれません。
要するにこれくらい投資顧問が助言内容の責任を取ってくれるかどうかは利用者の立場としては重要なのです。
そこでこのページでは「投資顧問おすすめ.com」を運営し、実際に投資顧問を利用している管理人が投資顧問は自社の過失の責任を取るのか、そして彼等の責任を追及する際の注意点等についてまとめてみました。
このページの目次
原則は一切責任を負わない
実はこの見出しにあるように投資顧問は原則としてどんな助言をしても責任は取りません。
なぜなら、投資顧問会社は金融庁側によって定められた法律によって「損失補てん」を含めた助言のミスに対する責任を背負うことを禁止されているからです。
それに原則としてどの投資顧問も契約時の契約書に「助言で生じた投資結果に対しては一切責任を負わない」と一筆を記載しております。
この一筆は契約書の右端や真ん中といった目立たない所に記載されているケースが多いですが、記載された契約書に利用者が同意した以上、責任の追及は原則としてできないのです。
一応投資顧問契約書を見る
先ほど投資顧問は原則として責任を負わないと言いましたが、責任の追及を行いたい状況が生まれましたら念のために契約書を確認しましょう。
どうしてこの契約書を確認するというひと手間が重要かというと、責任の追及ができるかどうかは契約条項次第だからです。
しかもあまり知られていませんが、投資顧問の中にはそもそも契約時の契約書に問題があるケースもあります。この契約内容に問題があるケースの代表格としてはこちらの3パターンがあります。
- 成果に責任を負わないという記載がない
- 事実上の損失補填のような記載がある
- 契約で定めた業務と提供業務が異なる
こういったケースではいくら投資顧問側は「責任を取らない」という原則があるとはいえ、契約書自体に問題がある以上、契約内容の問題点を論拠に異議申し立てをすることも不可能ではありません。
この点を考えると投資顧問側の責任の追及を行いたいような事態が発生した場合は、「責任を問うのは難しいことを念頭に入れながらも一応契約書を隅々まで見る」という行動を取りたいですね。
責任の追及が可能な4ケース
これから紹介するケースはあくまで例外中の例外ですが、投資顧問側の契約書に不備が見られないケースでも投資顧問側の責任を追及できることもあります。
この例外ケースにはどんなものがあるかをご理解頂くために、例外的に投資顧問側の責任を追及できる4つのケースを一覧にしてみました。
- 明らかな嘘があるケース
- 契約内容が一任契約
- 助言者側に重過失があるケース
- 争点が助言内容ではないケース
ここで取り上げた「投資顧問は責任を負わない」という原理原則に該当しない4つの例外ケースの詳細については上から順番にご紹介します。
明らかな嘘があるケース
まず1つ目の契約担当者が嘘をついているケース。
具体的には、うちは絶対に損を出させませんと営業担当者が口で言ってしまったり、広告で「利益が必ず出る」といった断定的な表現をしていたケース。
こういったケースでは詐欺罪や誇大広告をはじめとした「不当表示防止法」に該当します。この場合、損失の補填に対する責任の追及というよりも契約の無効や詐欺を論拠に投資顧問側の失点を責められます。
ただし、この「嘘を立証」するにはICレコーダーによる契約時の録音や誇大広告の写真を収めるといった行為を行い、投資顧問側の失点を法廷の場で客観的に示す必要があるので、難易度はかなり高いです。
契約内容が一任契約
「投資顧問側に責任の追及ができない」という原則の2つ目の例外ケースは、投資顧問との契約形態が投資助言契約ではなく、投資一任契約の時。
この場合、「投資顧問は損失の補填をしてはいけない」という金融庁が投資顧問側に課したルールの適応外になります。つまり、契約形態が投資一任契約であれば、投資顧問側に明らかな失点があれば、その失点に対する責任を追及することができるのです。
ちなみに、「投資一任契約って何?」と思いましたら、投資助言契約と投資一任契約の違いについてまとめているこちらをご覧ください。
助言者側に重過失があるケース
次にご紹介する「投資顧問は責任を追わない」という大原則の3つ目の例外ケースは投資顧問側に重過失が認められるケース。
例えば「推奨銘柄の売却サポートを行います!」と言ったにも関わらず、契約期間中に一度も行われずに損失が発生したケースや、投資顧問側のシステムエラーが原因で損失が生じるケースが該当します。
こういったケースで利用者側に損失を含めた何らかの不都合が発生した場合、重過失や契約不履行を理由に責任の追及を行える可能性があります。
ただし、発生した損失等に関してはどこまで責任を取ってもらえるかはケースバイケースですし、重過失であることが認められる必要もあります。この立証が難しいのは言うまでもありません。
争点が助言内容ではないケース
4つ目の「投資顧問は損失を負わない」の例外ケースは責任の追及を求める争点が助言内容ではないケース。
具体的には投資顧問との契約時に提供した個人情報が投資顧問側の不備で流失したり、投資顧問側が送付したメールにウィルスが含まれたケースが該当します。
こういったケースでは責任の追及ポイントが「助言による損失」ではないので、責任の追及は十分可能です。
ただし、このケースでも契約書の中に「個人情報の流失は一切責任を取らない」といった一筆があれば責任は問えないですし、そもそもここまでの問題が発生するケースは非常に稀です。
気になることは弁護士に相談
改めての話になりますが、ここまでの内容の総括をすると、「投資顧問は原則責任を負わないが、例外ケースもある」ということになります。
ただし、ここでポイントになるのが、例外ケースに該当するかどうかの基準。
この例外ケースに該当する代表的なケースはこれまでご紹介しましたが、例外ケースに該当するかどうかは結局のところ、あなたが決めるのでなく、法廷の場で決まります。
この点を考えると、投資顧問に責任を問いたくなる事態が発生したり、「これは投資顧問側の失点だろう・・・」と思った場合、まずは弁護士をはじめとした法律のプロに相談をして見解を伺うことをおすすめします。
弁護士に相談、と聞くとハードルが高いように思えますが、法テラス等の公的な機関を利用すれば無料で弁護士の知見が借りられます。
このひと手間を踏み、裁判をすることが割に合うと判断ができれば、法定の場で投資顧問の責任を問うのが良いですし、弁護士の顧問料が無駄になるのでしたら抗議を控えるのが一番。
投資顧問選びには力を入れる
このページのまとめになりますが、余程特殊なケースではない限り、投資顧問側の責任を追及することは不可能です。
この「投資顧問の責任を追及するのは難しい」というのは利用者の側としては大変不利な条件ですが、「投資は自己責任」である以上、ある意味仕方ありません。
つまり投資顧問を利用する際には「投資顧問のミスは契約者の責任」、というある種の自己責任論の許容が必須になるのです。
この点を考えると投資顧問を利用するのでしたら、責任の追及をしなくてはいけないケースに見舞われる状況を想定しなくてもよさそうな実力の面でもサポートの面でも優れた投資顧問を選ぶことが求められます。
このような特徴を持ち、サポートの面においても銘柄の予測率の面においても非常に秀でた投資顧問の探し方と会社名の候補についてはこちらのページで特集しているのでよろしければどうぞ。